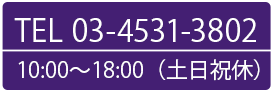コピー用紙に線が入る原因はアレだった!印刷物に線が入る原因と対処を解説

コピー機(複合機)を使っていると、印刷用紙に黒い線や白い線が入ってしまったという経験はありませんか?
実は印刷用紙に線が入るトラブルは自分自身で簡単に解決できる事もあります。
また、印刷用紙に線が入るパターンはいくつかありますので最初にご紹介させていただきます。
・コピーをした時に黒い線が入る場合
・プリントアウトした時に黒い線が入る場合
・プリントアウトした時に白いが入る
上記のように線が入るパターンによって、コピー機(複合機)の対処方法が異なります。
自分自身で簡単な対処によってすぐに改善できる症状もあれば、保守業者を呼ばなければ改善できないケースもあります。
今回は、その症状別の対処方法について解説させていただきます。
コピー機(複合機)の保守業者に依頼すると改善されるまでに時間を要し、その間はコピー機の利用ができず仕事に支障をきたしてしまいます。
簡単な対処で改善できれば、すぐにコピー機を利用する事ができるようになりますので、知識として身に着けておきましょう。
また、これからコピー機(複合機)の導入を検討している方は是非、参考にしてみてください。
症状1:コピーをした時に黒い線が入る場合の対処方法

コピー機(複合機)でコピーをした時、印刷物に黒い線が入る症状の対処方法をご紹介いたします。
コピー機でコピーをする際は「自動原稿送り装置(ADF)」と「原稿台ガラス」の2通りがあります。
「自動原稿送り装置(ADF)」で黒い線が入る場合と「原稿台ガラス」で黒い線が入る場合では対処方法が異なりますのでそれぞれご紹介させていただきます。
⇒コピー機の便利機能ADF(自動原稿送り装置)でできること!!気を付けるべき注意点
「自動原稿送り装置(ADF)」で黒い線が入る場合
自動原稿送り装置(ADF)は印刷用紙をセットしてコピーやスキャン、FAXなどが利用できる装置となります。
ADFに複数枚の印刷用紙をセットできるので処理時間などを短縮してくれるとても便利な機能です。
自動原稿送り装置(ADF)でコピーした印刷物に黒い線が入る場合は原稿台ガラスの左側の細長いガラスに汚れが付着している可能性が高いです。
または原稿台の細長いガラスに蓋をしている原稿台カバーに汚れが付着している場合があります。
ADFでコピーをする場合は印刷用紙がローラーを通って、読み取りガラスでスキャンを行います。
そのスキャンをする場所が原稿台ガラスの左側の細長い箇所になります。
その細長い読み取りガラスが汚れている場合、汚れが影になってしまい印刷したときに黒い線になって現れます。
対処方法は簡単です。
まずは柔らかい布で読み取りガラスと原稿台カバーの汚れをふき取りましょう。
乾拭きで汚れが落ちない場合は水拭き、それでも落ちない場合はオフィス機器専用洗剤のOAクリーナーを使用しましょう。
コピー機(複合機)は精密機械になるので乱暴に拭かないようにしましょう。
また、水分や洗剤が残ってしまうと故障の原因になってしまうので、必ず最後は乾拭きして水分などを拭き取りましょう。
⇒コピー機の便利機能ADF(自動原稿送り装置)でできること!!気を付けるべき注意点
「原稿台ガラス」で黒い線が入る場合
続いて、コピー機の「原稿台ガラス」に印刷用紙を置いてコピーをした場合の症状について解説させていただきます。
自動原稿送り装置(ADF)からのコピーと同じように原稿台ガラスに汚れが付着している可能性が高いです。
黒い線が入る理由としてはADFの症状と同じように、読み取りガラスの汚れが影になってしまい印刷したときに黒い線になって現れてしまいます。
こちらも対処方法は同じで、読み取りガラスを掃除すれば解消される可能性が高いです。
柔らかい布で読み取りガラスと原稿台カバーの汚れをふき取りましょう。
乾拭きで汚れが落ちない場合は水拭き、それでも落ちない場合はオフィス機器専用洗剤のOAクリーナーを使用しましょう。
症状が改善されない場合はガラス面の内部に問題があります。
コピー機内部を触ると故障に繋がる可能性があるので無理をせずに保守業者を依頼をしましょう。
⇒コピー機(複合機)を長持ちさせる為に!!セルフメンテナンスの方法を解説
■お安い大型レンタルをお考えの方はこちら(業界でもびっくりな価格表)
■リースをお考えの方はこちら(メーカーに我々が直接値引き交渉ができるので安い)
■小型機のレンタルをお考えの方はこちら(1週間無料お試し)
症状2:プリントアウトした時に黒い線が入る場合の対処方法

続いて、上記でお伝えしたコピー時の症状ではなく、プリントアウトした時に黒い線が入る症状の対処方法をご紹介いたします。
プリントアウトとはパソコンやスマートフォンなどの電子機器で作成したデータや情報をコピー機(複合機)を利用して用紙に印刷する事を指します。
プリントアウトした時、印刷物に黒い線が入ってしまう場合はコピー機内部の汚れが原因となります。
内部の清掃は慎重に作業をしなければ故障の原因になってしまう可能性があります。
必ずコピー機の電源を落としてから各メーカーのマニュアルを確認して作業をするようにしましょう。
また、クリーニング機能という自動で内部を清掃してくれる機能を搭載しているコピー機もあります。
一通り作業をしても改善されない場合は、コピー機(複合機)の心臓部に汚れなどが付着している可能性がありますので保守業者に依頼をしましょう。
コピー機(複合機)は精密機械になるので特に内部清掃する際は無理をせずに保守業者に依頼をする事をおすすめします。
⇒コピー機の印刷汚れを消す方法!自分で出来る簡単クリーニング方法とは?
プリントアウトした時に黒い線が入る症状として、もうひとつの原因として「結露」が起こっている可能性があります。
結露は冬場によくみられる症状になります。
コピー機(複合機)を導入している部屋が冷え切っているときに暖房をいれると、急激に部屋の温度が上がり、コピー機との温度差で結露が起こってしまいます。
ゆっくり部屋を暖めるというのも難しい事なので結露は仕方ない症状になります。
結露は寒暖差がなくなると収まるので。しばらく待って様子をみてください。
コピー機にクリーニング機能がある場合はクリーニング機能も試してみましょう。
結露の対処方法など下記コラムにまとめてますので気になる方は確認してみてください。
⇒寒くなるとコピー機(複合機)が故障する原因は「〇〇」だった!!
症状3:プリントアウトした時に白い線が入る場合の対処方法
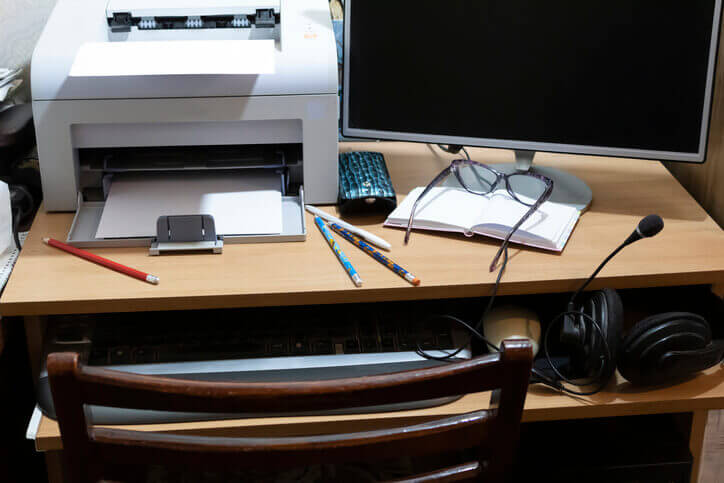
続いて、プリントアウト時に白い線が入る場合の解説をさせていただきます。
黒い線ではなく、白抜きの線が入ってしまう症状の事を指します。
印刷物に白い線が入ってしまう場合はコピー機内部の部品が原因で不具合を起こしている可能性が高いです。
まずはコピー機(複合機)にクリーニング機能がある場合はクリーニング機能を試してみましょう。
それで改善されない場合はコピー機の保守業者に依頼をしましょう。
黒い線は清掃すれば比較的、改善される事は多いですが、白い線はご自身で直すのは困難です。
コピー機は精密機械になるので内部を触ると故障の原因になるので、無理に触らないようにしましょう。
このプリントアウトした時に白い線が入る症状は危険信号がでています。
コピー機(複合機)の劣化が考えられ、ほとんどの場合は保守業者が内部のメンテンナンス部品を交換して改善されるかどうかです。
その時は改善されても少し時間がたつと、また白い線が入る事もあります。
⇒業務用コピー機の保守メンテナンス体制を比較!おすすめメーカーをご紹介
■お安い大型レンタルをお考えの方はこちら(業界でもびっくりな価格表)
■リースをお考えの方はこちら(メーカーに我々が直接値引き交渉ができるので安い)
■小型機のレンタルをお考えの方はこちら(1週間無料お試し)
印刷物に線が入る原因はアレだった!?

コピー機(複合機)の印刷時に印字トラブルが起きてしまった場合、ご自身で簡単に解決できれば問題ないですが、ほとんどの場合が保守業者に依頼する必要があります。
また、ご自身でコピー機を直してもすぐに同じ症状に戻ってしまう事もあります。
保守業者ではなく、セルフメンテナンスはガラス面や内部の拭き清掃程度です。
それでも改善されない場合、印刷用紙に線が入ってしまう事や印字トラブルの原因はほとんどがドラムカートリッジ(感光体)によるものです。
コピー機(複合機)には様々な部品が内部にあり、100%ドラムカートリッジが原因というわけではありません。
ドラムカートリッジはトナーカートリッジと同じくコピー機(複合機)の消耗品の一つになり、印刷を行う際に毎回消耗していくものになりますので定期的な交換が必要になります。
コピー機のレーザー方式ではドラムカートリッジによってトナーを熱処理し、紙に定着させ印刷を行います。
このトナーを定着させるのがうまくいかず、印刷不良を起こす事が多々あります。
コピー機(複合機)は精密機械になり、コピー機内部に様々な部品が搭載されております。
線が入ってしまう以外にも、印刷物に点々がついたり、文字がかすれたりといった症状など様々です。
レーザー方式のコピー機(複合機)は先ほどお伝えした通り、熱処理を行い、印刷をするので無理にコピー機内部を触らないようにしましょう。
⇒コピー機のインクジェットとレーザープリンターは何が違うの?メリットとデメリットを解説
■お安い大型レンタルをお考えの方はこちら(業界でもびっくりな価格表)
■リースをお考えの方はこちら(メーカーに我々が直接値引き交渉ができるので安い)
■小型機のレンタルをお考えの方はこちら(1週間無料お試し)
ドラムカートリッジは清掃できる!?

印字不良のほとんどはドラムカートリッジが原因となる為、ドラムカートリッジを新しいものに交換することが最も効果的な対処方法と言えます。
ただし、軽度の症状であれば機械内部の簡単な清掃を行うことですぐに解決することもありますので、ここではその方法について解説していきます。
ドラムカートリッジの清掃方法としては、大きく分けて自動クリーニングと手動クリーニングの2種類があげられます。
自動クリーニング
まず自動クリーニングですが、これは機械にクリーニングを行わせる方法で、ほとんどのコピー機(複合機)に搭載されている機能になります。
パソコンでプリンタードライバーから指示を出す方法と機械の操作パネルから指示を出す方法がありますが、いずれもメーカーや機種によって異なる為、各ドライバーや各メーカーのホームページで確認するようにしましょう。
手動クリーニング
もう一つの方法として手動クリーニングがありますが、これはコピー機(複合機)内部に格納されているドラムカートリッジを直接清掃する方法です。
こちらも清掃方法は機種やドラムカートリッジの型によって異なりホームページなどで確認出来る場合がありますが、清掃含めドラム部分については保守業者のみ取り扱いとなっている場合もありますので注意が必要です。
トラブルを避ける為にも出来るだけ保守の窓口に確認すると良いでしょう。
⇒業務用の大型コピー機(複合機)の正しいクリーニング方法とは?自分で出来るの?
印字不良がドラムカートリッジが原因でないケース

印刷物に線が入る、点々が出る、文字がかすれるなどのトラブルのほとんどはドラムカートリッジが原因ですが、他の箇所が原因となっているケースもあります。
ここではおさらいも含めて、印字不良の原因になっているパターンとその対処法についてご説明します。
原稿を置くガラス面が汚れている場合
コピーやスキャンで線が入る場合や点々が出る場合は、原稿を置くガラス面や原稿をおさえるカバー内部のクッション部分が汚れているケースも考えられます。
清掃する際は、柔らかい布に水か中性洗剤を含ませて硬く絞ってから汚れを拭き取るようにしましょう。
それでも汚れが取れない場合やガラス面の内部に汚れがある場合はメンテナンスを呼ぶ必要があります。
ADF(自動原稿送り装置)を使った際に汚れが出る場合
ADFとはコピーやスキャンの際に複数枚の原稿をセットして一気に読み取りを行えるもので、一般的にコピーの際に原稿をおさえるカバーの上部に搭載されています。
こちらは通常原稿を置くガラス面の横にADF用の細長い読み取り分がありますので、まずはその部分を清掃します。
通常のガラス面同様ADFの読み取り分にも原稿を抑える箇所がありますので、こちらも清掃します。
これらを清掃する場合にも、通常のガラス面を清掃する場合と同様に柔らかい布に水か中性洗剤を含ませて硬く絞ったもので汚れを拭き取るようにしましょう。
清掃方法については機種により若干異なる場合がありますが、通常はメーカーのホームページで確認が出来ます。不明な場合は保守の窓口に連絡しましょう。
ローラーが汚れている場合
ドラムカートリッジが原因でなく原稿台にも特に汚れが見られない場合、紙を送るローラーが汚れているケースが考えられます。
印刷をする際、用紙トレイから給紙された紙は一般的に機械側面分にある通過部分を通って最後に排出口に出力されます。
それぞれローラーがありますので、こちらも柔らかい布に水か中性洗剤を含ませて硬く絞ってから汚れを拭き取るようにしましょう。
ただし、ガラス面を清掃する場合と異なり機械内部に触れることになりますので保守窓口に確認をとって行うようにしましょう。
■お安い大型レンタルをお考えの方はこちら(業界でもびっくりな価格表)
■リースをお考えの方はこちら(メーカーに我々が直接値引き交渉ができるので安い)
■小型機のレンタルをお考えの方はこちら(1週間無料お試し)
まとめ
今回は用紙に線が入るケースを始め、点々が出たり文字がかすれたりする場合の原因と対処方法についてお話しました。
ドラムカートリッジが原因となっていることが最も多く、その他にはガラス面やローラーの汚れなどが原因となっているケースをご紹介しました。
その中で、やはり消耗品やメンテナンス部品が原因となる場合が多く使用していくうちにどうしても印字不良が出てしまいます。
メンテナンスを呼ぶのが確実ですが、すぐに復旧させたい場合やメンテナンスが来るまでに対処したい場合には是非ご紹介した方法をお試しください。
ただし、機械内部に触れる場合や方法に不明点がある場合は保守窓口に確認するようにしてくださいね。

 お問い合わせ
お問い合わせ